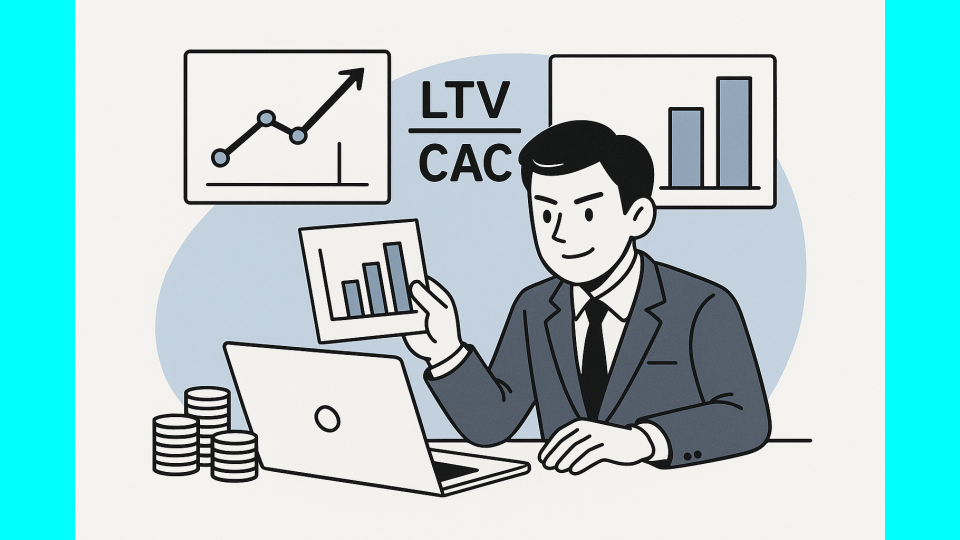
知っておきたいマーケティング用語:ユニットエコノミクスとは何か ― 製造業BtoBで単価の幅がある商品の場合の考え方
🧩 ユニットエコノミクスとは何か
「ユニットエコノミクス(Unit Economics)」とは、
1顧客あたり、または1取引あたりの収益性を可視化する指標です。
SaaSやサブスクリプションの世界でよく使われる言葉ですが、
製造業BtoBでも「マーケティングの投資判断」や「営業活動の効率化」を考える上で、非常に重要な考え方です。
💡 なぜ製造業にも必要なのか
製造業の営業活動は、一般的に次のような特徴を持ちます。
- 商談ごとの単価のばらつきが大きい
- リード獲得コストや展示会出展費が重い
- 案件化までのリードタイムが長い
このため、平均的な「顧客獲得コスト(CAC)」や「顧客生涯価値(LTV)」をそのまま出すのが難しいのです。
しかし、だからこそ「ユニットエコノミクス」で1件あたりの収益構造を見える化することで、
「どこにどれだけ投資すべきか」「どの商談群を優先すべきか」が判断できるようになります。
🧮 基本式:LTV / CAC
ユニットエコノミクスの基本構造は次の通りです。
ユニットエコノミクス = LTV ÷ CAC
- LTV(Life Time Value):1顧客が生涯にもたらす利益
- CAC(Customer Acquisition Cost):1顧客を獲得するのにかかったコスト
SaaSであれば「1ユーザー」単位で計算されますが、
製造業では「1案件」「1顧客」「1製品ライン」などの粒度で見ることが多いです。
⚙️ 製造業BtoBにおける計算の難しさ
たとえば、製造業の商材では以下のような構造がよくあります。
| 商材タイプ | 単価 | 粗利率 | 案件頻度 |
|---|---|---|---|
| 標準機 | 100万円 | 40% | 年10件 |
| カスタム機 | 500万円 | 30% | 年3件 |
| 特注ライン | 2000万円 | 25% | 年1件 |
※ スクロールで全体を表示できます。
これらを平均して「1顧客あたりLTV」を出すと、実態を正確に反映しません。
単価のばらつきが大きいため、案件タイプ別に分けて分析する必要があります。
🧭 ステップ①:案件タイプ別に「LTV」を算出する
まず、LTVを「顧客あたり」ではなく「案件タイプあたり」で整理します。
LTVの計算式(製造業BtoB版)
LTV = 平均単価 × 粗利率 × 継続年数(またはリピート頻度)
例:
標準機の場合
→ 100万円 × 40% × 3年 = 120万円
カスタム機の場合
→ 500万円 × 30% × 2年 = 300万円
このように、単価だけでなく「リピート性」や「利益率」も考慮してLTVを出します。
1顧客が継続的に購入する場合は、さらに平均継続期間を掛け合わせます。
🧭 ステップ②:リード獲得から商談化までのCACを算出する
製造業では、展示会や紹介、Webマーケティングなど、
リードの獲得経路によってコストが大きく異なります。
CACの計算式
CAC = リード獲得コスト ÷ 受注率
たとえば:
| リード獲得経路 | リード獲得単価 | 受注率 | CAC(1受注あたり) |
|---|---|---|---|
| 展示会 | 5万円 | 5% | 100万円 |
| Web広告 | 2万円 | 2% | 100万円 |
| 既存顧客紹介 | 0.5万円 | 10% | 5万円 |
※ スクロールで全体を表示できます。
このように、同じ「1件受注」に至るまでのコストがまったく違うことがわかります。
CACが高いチャネルは「リード精度」や「ナーチャリング施策」を改善する対象になります。
🧭 ステップ③:ユニットごとの採算を比較する
それぞれの商材タイプ別にLTV / CACを計算します。
| 商材タイプ | LTV | CAC | LTV/CAC |
|---|---|---|---|
| 標準機 | 120万円 | 100万円 | 1.2倍 |
| カスタム機 | 300万円 | 150万円 | 2.0倍 |
| 特注ライン | 500万円 | 300万円 | 1.6倍 |
※ スクロールで全体を表示できます。
✅ 解釈のポイント
- 1を超えていれば黒字構造(LTV > CAC)
- 2を超えていれば投資効率が良い
- 1未満なら赤字構造(受注しても費用回収できない)
製造業のBtoBでは「展示会出展費+営業工数」が重くのしかかるため、
1.5倍以上を目標にすると安定します。
🧭 ステップ④:幅のある単価を扱う場合の実践的アプローチ
単価が100万円〜2000万円のように幅広い場合は、
中央値や加重平均を使うのが現実的です。
1️⃣ 加重平均を使う方法
平均単価 = Σ(単価 × 件数) ÷ Σ(件数)
例:
| 商談タイプ | 単価 | 件数 | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 小型装置 | 100万円 | 20件 | 2000万円 |
| 中型装置 | 500万円 | 5件 | 2500万円 |
| 大型装置 | 2000万円 | 1件 | 2000万円 |
| 合計 | - | 26件 | 6500万円 |
※ スクロールで全体を表示できます。
平均単価 = 6500万円 ÷ 26件 ≒ 250万円
つまり「平均的な案件」は250万円規模としてLTVを出す。
これで極端な高単価案件の影響をならすことができます。
2️⃣ パターン別にユニットを分ける方法
単価の幅が大きいほど、「ユニットを分けて分析する」方が精度が上がります。
たとえば:
- 小型装置群(100〜300万円)
- 中型装置群(300〜800万円)
- 大型ライン群(800万円〜)
それぞれの群で「LTV/CAC」を出すことで、
どの価格帯がもっとも収益性が高いかを明確にできます。
📊 ステップ⑤:営業リソース配分に活かす
ユニットエコノミクスを出したら終わりではありません。
重要なのは、営業リソースをどこに集中させるかの判断材料として使うことです。
| 商材タイプ | LTV/CAC | 営業工数 | 改善方針 |
|---|---|---|---|
| 標準機 | 1.2倍 | 小 | ナーチャリング改善で効率化 |
| カスタム機 | 2.0倍 | 中 | 重点営業対象に設定 |
| 特注ライン | 1.6倍 | 大 | 見積・提案コスト削減で改善 |
※ スクロールで全体を表示できます。
→ リターン効率が高い「中単価商材」に注力するなど、戦略的な配分が可能になります。
🔁 ステップ⑥:継続的にモニタリングする
LTVやCACは固定ではなく、
営業の質・リードの質・受注率によって常に変動します。
特に以下の指標を定期的にトラッキングすることが大切です。
| 指標 | 目的 |
|---|---|
| リード獲得単価(CPL) | マーケ効率を測る |
| 商談化率 | インサイドセールスの精度を測る |
| 受注率 | 営業の決定力を測る |
| 粗利率 | 提案品質・購買条件を測る |
| 平均リピート間隔 | 継続率を測る |
※ スクロールで全体を表示できます。
これらを掛け合わせることで、LTV/CACの構造変化を把握できます。
⚡ 事例:工作機械メーカーの場合
ある工作機械メーカーでは、以下のように分析しました。
| 区分 | LTV | CAC | LTV/CAC | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 汎用小型機 | 80万円 | 100万円 | 0.8倍 | 赤字構造。展示会依存を縮小 |
| 中型機 | 300万円 | 120万円 | 2.5倍 | 重点投資対象 |
| 大型ライン | 2000万円 | 600万円 | 3.3倍 | 高利益だが営業負荷が高い |
※ スクロールで全体を表示できます。
→ この結果、「中型機」向けにWebコンテンツと動画展示会を強化する方針を決定。
展示会出展を絞り、リードの質を高めたことでCACが20%改善しました。
🚀 製造業マーケティングでの応用ポイント
- 「1件あたりの収益構造」を定量化できる
- 受注率や工数などの営業データを結びつけられる
- 投資判断を感覚ではなくデータで行える
とくに、展示会・Web広告・営業訪問などの施策ごとに
「ユニットエコノミクス」を算出して比較することで、
本当に儲かる施策と“なんとなく続けている施策”を切り分けることができます。
🧭 まとめ:ユニットエコノミクスで“投資判断”を科学する
製造業BtoBでは、単価の幅が広く、商談ごとの利益率もバラつきます。
しかし、LTV/CACのフレームを用いて案件タイプ別・価格帯別に整理すれば、
「どこにリソースを集中させるべきか」が明確になります。
感覚ではなく、データで投資する。
それが、製造業におけるユニットエコノミクス活用の本質です。
✍️ この記事のポイントまとめ
- ユニットエコノミクス = LTV ÷ CAC
- 単価の幅がある場合は「群ごと」または「加重平均」で整理
- 1を超えれば黒字、2を超えれば投資効率良好
- 営業・マーケ両面のリソース配分判断に使える
- 継続的なLTV/CACモニタリングが経営改善の起点になる





