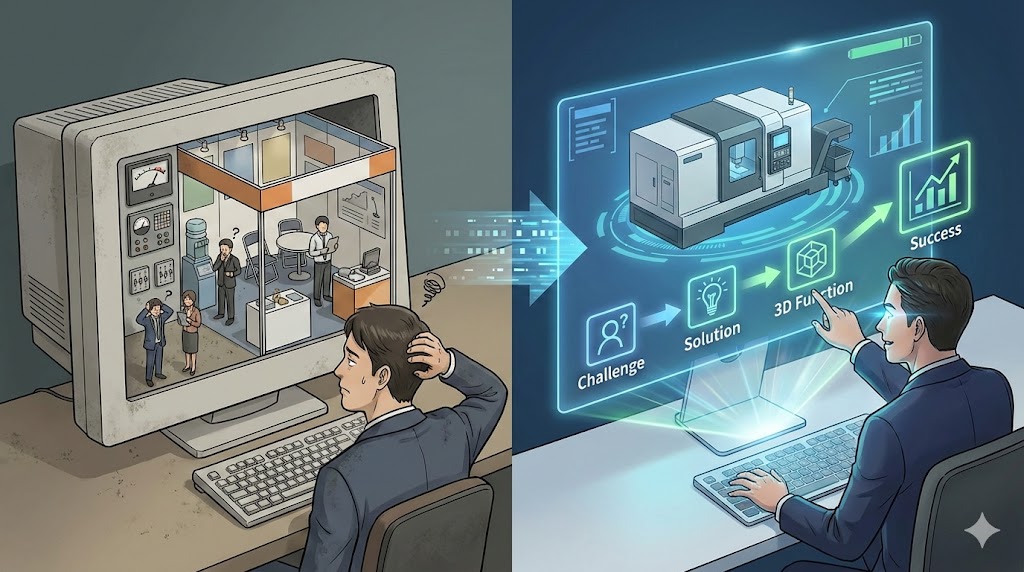
なぜ“リアル展示会の延長”ではオンライン展示は失敗するのか──製造業マーケティングのための体験DX思考
コロナが流行った時期に対面営業やイベントが規制された際には、製造業のマーケティングにおいて「展示会のデジタル化」は避けて通れない課題となりました。
多くの企業がバーチャルブースを制作し、Web上での集客を試みていました。しかし、その取り組みはコロナが沈静化したと共になくなり、今では見る影もありません。
おそらく、成果が得られなかったのでしょう。
バーチャルブースを開催することは決して軽い費用負担ではありません。
せっかく予算と時間をかけて構築したのに、なぜ成果に結びつかないのか。 その理由は、実は非常にシンプルです。
リアル展示会の感覚を、そのままWebに持ち込んでしまっているからです。
つまり、空間の体験設計をWebの体験設計に置き換えられていない。
この記事では、なぜこの誤解が起こり、どうすれば成果につながるオンライン展示を設計できるのか、
Vizlaboの“体験DX”思想に基づいて解説します。
✅ 結論:オンライン展示は「雰囲気」ではなく「理解の順序」を設計する場所
リアル展示会は
- 物理空間
- 人の導線
- 偶然の遭遇
- 営業の対話
で成立しています。
一方、オンライン展示は
- 無限の情報空間
- 自発的なクリック
- 離脱自由
- 文脈の提示が必要
というまったく別の環境。
リアルは“空間の演出”、Webは“理解の演出”が必要
ここを理解せずに、ブースを3Dで再現したり、動画を流したりしても成果は出ません。
◆ リアル展示会がうまく機能する理由
リアル展示の強みは、以下の“非デジタル要素”です。
| 強み | 内容 |
|---|---|
| 偶然性 | 通りかかった人が目に留める |
| 空気感 | 空間の熱量・臨場感 |
| 五感 | 音・距離感・サイズ感 |
| 営業の介在 | 反応を見て説明を変えられる |
言語化するとこうです。
リアル展示は、予定調和ではなく“環境が語る”体験
だから、多少説明が不十分でも“雰囲気で伝わる”。
◆ オンライン展示が苦戦する理由
一方で、オンラインでは次の条件が成立します。
| 制約 | 内容 |
|---|---|
| 自発性 | 見る側が能動的にクリックしないと始まらない |
| 競合は1クリック先 | タブを閉じれば他の仕事に戻れる |
| 情報密度が高い | テキスト・動画・資料が無限に存在 |
| 論理優位 | 直感よりも理解が優先される |
つまりこういうこと。
オンライン展示では“興味の誘導”と“理解の順序”がないと即離脱
だから、リアルと同じ“置き方”では通用しない。
◆ よくある失敗例5つ
| 失敗例 | なぜうまくいかないか |
|---|---|
| ブースを3Dで再現 | 空間の意味がWebでは消える |
| 動画を流すだけ | “理解導線”がないので飽きる |
| PDFダウンロード | 読まれない・体験がない |
| ボタンだらけ | UIが思考の負担になる |
| 製品紹介から始める | “なぜ見るべきか”の文脈が先 |
これらはすべて、
空間的思考 → 体験設計的思考への移行が不足している。
◆ オンライン展示が成功する条件
オンライン成功の鍵は、導線の設計です。
必要なのは“理解のシナリオ”
例:
- なぜこの製品が必要か(課題提示)
- どう改善されるのか(価値提示)
- どの部分が優れているか(構造/機能理解)
- 実際の動作イメージ(3DCG/動画)
- 導入事例(信頼)
- 行動動線(資料DL・商談予約)
オンライン展示は
**「展示」ではなく「ストーリー体験」**なのです。
◆ Vizlabo方式:空間 → 理解へ翻訳する
Vizlaboがやっていることは
展示の翻訳
- 空間の魅せ方
→ 理解の魅せ方 - “偶然の出会い”
→ 意図的な導線 - 営業の会話
→ ナレーション・視線誘導・アニメ
Vizlabo展示の要素
| 要素 | 目的 |
|---|---|
| 3DCGで動作理解 | 「見れば分かる」を作る |
| 視線誘導UI | “どこを見るか”を迷わせない |
| ナレーション | “なぜそれが重要か”を伝える |
| 行動ログ | “誰が何に興味を持ったか”が分かる |
展示 × 3DCG × マーケティング
これがVizlaboの体験DXの核
◆ 失敗しないための原則
原則1:見せる前に、理解の順序を設計する
原則2:動画は“体験の部品”にすぎない
原則3:説明ではなく、“納得”を作る
原則4:UIは“視線を導くための道具”
原則5:展示は終わらない──常設で回す
◆ まとめ
- リアルとWebは別の体験構造
- 空間演出ではなく理解演出が必要
- オンライン展示はストーリー体験
- Vizlaboは展示の翻訳者
リアルの代替ではない。
オンライン独自の展示価値を設計する。
これが、成果が出る“体験DX”の思想です。





