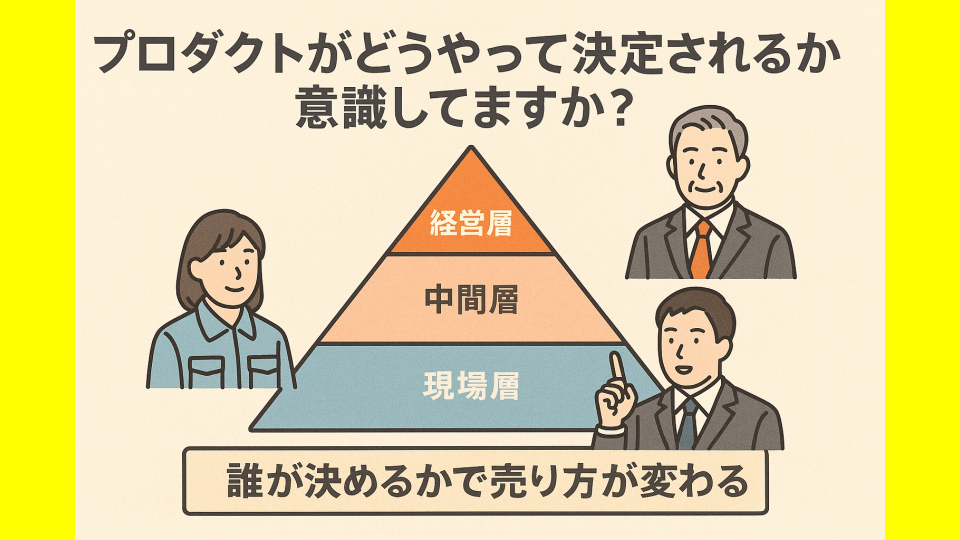
プロダクトがどうやって決定されるか意識してますか? ―意思決定構造を理解しないマーケティングは届かない―
BtoBマーケティングや営業活動をしていると、思わぬ壁にぶつかることがあります。
「担当者とは盛り上がるのに、なかなか話が前に進まない」
「資料を送っても反応が薄い」
「見積までは行くけど、最後の承認が下りない」
これらの原因の多くは、「プロダクトがどうやって決定されるか」を意識できていないことにあります。
つまり、意思決定の構造を理解せずにアプローチしているのです。
1. 意思決定構造を理解するとは何か
「この会社で、どういう流れで製品導入が決まるのか?」
この問いに明確に答えられる営業やマーケターは、意外と少ないのが現実です。
製造業やBtoBの商材の場合、購買の決定は一人では行われません。
複数の部門・複数の階層が関与する“合議的なプロセス”です。
その構造をざっくり整理すると、次の3層に分けられます。
| 層 | 主な役割 | 意思決定の特徴 |
|---|---|---|
| 現場層(担当者・主任クラス) | 問題発見・比較検討 | 現場の使いやすさ・実効性を重視。実務ベースの評価。 |
| 中間層(課長・係長クラス) | 導入判断の一次承認 | 効果とコストのバランス。部門の予算責任を負う。 |
| 経営層(部長・役員クラス) | 最終決裁・導入承認 | 経営戦略・ROI・リスク回避を重視。全社視点で判断。 |
この構造を理解しないままマーケティングを行うと、
- 現場には刺さるが決裁が下りない
- 経営には響くが現場に拒否される
といったギャップが生まれます。
2. トップダウン型とボトムアップ型
意思決定には大きく分けて2つのタイプがあります。
あなたの顧客はどちらでしょうか?
トップダウン型
- 経営層や部長クラスの意向で導入が決まる
- 「全社的に○○を標準化する」「コスト削減方針」など、方針主導
- 導入後、現場はその方針に従う
この場合、経営層へのメッセージ設計が最優先です。
ROI、リスク回避、他社との差別化、経営方針との整合性――
これらの文脈で訴求する必要があります。
ボトムアップ型
- 現場担当者が課題を感じ、上層部に提案
- 試験導入 → 成果報告 → 本導入という流れが多い
- 導入を“使う人”が主導して動く
この場合、現場担当者の「業務改善」「使いやすさ」「時短効果」に焦点を当てたメッセージが有効です。
現場で「これ、便利だね」「これならウチでも使えそう」と思ってもらうことが最初の一歩になります。
3. 価格帯によって意思決定構造は変わる
製品の価格帯によっても、意思決定の層やプロセスは大きく変わります。
| 価格帯 | 主な決定層 | 意思決定の特徴 |
|---|---|---|
| 〜50万円 | 現場・課長クラス | 承認権限内で決定可能。現場判断が早い。 |
| 50〜300万円 | 課長〜部長クラス | 複数部署・稟議フローあり。ROIが重視される。 |
| 300万円以上 | 部長〜役員クラス | 投資判断レベル。導入効果や全社戦略との整合が必須。 |
たとえば、同じソフトウェアでも
月額5万円なら課長決裁で済むが、年間契約600万円なら役員会案件になる。
つまり、価格帯が上がるほど、論点が経営寄りになるのです。
「便利そう」「見た目がいい」ではなく、
「全社に導入する意義があるか」「費用対効果が見込めるか」が焦点になります。
4. どこに向けてメッセージを発信すべきか
マーケティングの目的は、意思決定のどの層にどんな情報を届けるかを明確にすることです。
現場層へのメッセージ
- 実際の使い勝手や効果を感じられる具体的なデモや導入事例
- 「導入したら何分短縮できるか」「誰でも操作できるか」
- 製品ページ、チュートリアル動画、FAQなどが有効
中間層へのメッセージ
- コスト削減や業務効率化の実績
- 「○○部署で年間○○時間削減」「投資回収まで○ヶ月」
- 資料DL・ホワイトペーパーなどで“稟議用素材”を提供するのがポイント
経営層へのメッセージ
- 経営課題との接続(生産性向上、人材不足対応、リスク削減など)
- 短期ROIだけでなく「競争優位性」や「ブランド強化」の文脈
- セミナー、レポート、トップインタビューなどの“経営層向けコンテンツ”が効果的
5. 意思決定フローを可視化する
自社商材が「どの層」で止まりやすいのかを把握するために、
次のような図式化を行うと明確になります。
現場担当者 → 課長 → 部長 → 役員 → 社長
↑
(どこで止まっている?)
yaml
コードをコピーする
営業・マーケティングが一体となって、
「担当者から上にどう稟議が上がるのか」
「上層部はどのタイミングで関与するのか」
をヒアリング・仮説立てしていくことが重要です。
特に、現場からの稟議が上層部に届くまでには、**“翻訳”**が発生します。
現場の言葉(使いやすい・便利)を、上層部の言葉(効果・ROI)に変換する必要がある。
マーケティングコンテンツは、この翻訳を支援する役割を果たします。
6. 意思決定構造を理解するとメッセージが研ぎ澄まされる
たとえば、あなたが販売しているのが「製造業向けの3DCGシミュレーションソフト」だったとします。
- 現場層は「実機を使わず動作確認ができる」点に価値を感じる
- 中間層は「展示会の準備コストを下げられる」点を重視する
- 経営層は「営業効率化による利益率向上」に注目する
同じ製品でも、伝えるべきポイントがまったく異なります。
この構造を理解せずに「製品の機能」を一律に伝えても、刺さらないのです。
7. マーケティングは“意思決定の地図”を描く仕事
マーケティングとは、単にリードを集めることではありません。
顧客企業の中に存在する「意思決定の地図」を理解し、
どのルートで承認が下りるのかを設計する仕事です。
- 現場が使いたいと思う
- 課長が導入を承認できる
- 部長が予算を確保する
- 役員が経営戦略に組み込む
この流れを意識すれば、あなたの発信するメッセージは自然と立体的になります。
「誰に」「どの段階で」「何を伝えるか」――
それを意識するだけで、営業効率は大きく変わります。
8. まとめ:プロダクトは“誰が決めるか”で売り方が変わる
プロダクトがどう決定されるかを理解することは、マーケティングの出発点です。
- トップダウン型かボトムアップ型か
- どの層が決裁権を持つのか
- 価格帯によってどこまで上がるのか
これを把握していないと、“誰に何を伝えるか”がぼやけてしまい、成果は上がりません。
逆に、意思決定構造を理解すれば、
あなたの提案は「刺さる相手」に「適切な言葉」で届くようになります。
プロダクトの機能を伝える前に、まずは相手企業の「決め方」を知る。
それこそが、BtoBマーケティングの最も戦略的な第一歩です。
🟢 次のステップ
- あなたのターゲット企業の典型的な意思決定フローを図にしてみる
- 価格帯別に「誰が決めているか」を整理する
- それぞれの層に向けたメッセージとコンテンツを再設計する





