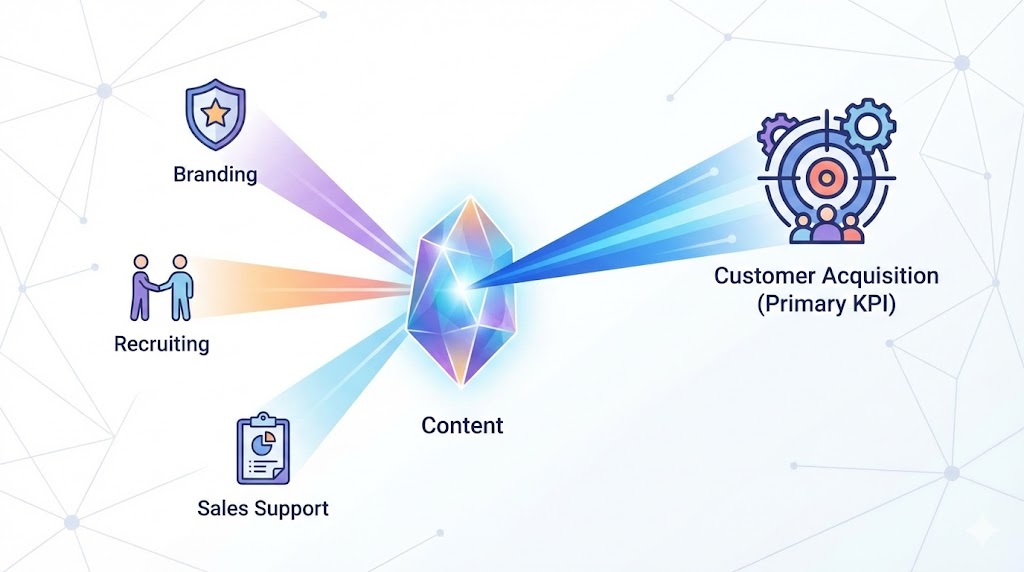
コンテンツに集客以外の意義を持たせるべきか ― コンテンツマーケティングのKPI再考
コンテンツマーケティングを実践していると、必ずぶつかる問いがあります。
「コンテンツの目的は集客だけでいいのか?」
それとも「ブランディングや採用活動など、より広い意味での経営貢献まで含めるべきなのか?」
この問いは、一見すると些細な運用上の議論に見えますが、実はコンテンツマーケティングの本質を突くものです。
なぜなら、コンテンツが持つ価値は単なる「見込み客の流入」を超えて、企業のあらゆる活動に波及するからです。
本記事では、コンテンツの役割を「集客」と「それ以外」に分け、どこまでKPIに取り入れるべきかを整理します。
コンテンツの基本的な役割:集客
まず、コンテンツマーケティングが始まった背景を振り返りましょう。
- SEOのためのブログ記事
- SNSシェアを狙った記事や動画
- 資料DLによるリード獲得
いずれも「新しい見込み客を集める」ことが主目的でした。
つまり、**流入数・リード数・CPA(顧客獲得単価)**などが直接的なKPIになります。
この視点は今でも揺るぎません。企業がコンテンツに投資する以上、顧客獲得や売上につながる効果が最も測定しやすく、経営陣に説明しやすいからです。
集客以外の役割:ブランディング・採用・営業支援
しかし実際にコンテンツを運用していくと、「副次的に効いている効果」が見えてきます。
1. ブランディング
- 業界の知見を深く発信している企業は「専門性が高い」「信頼できる」と認識される
- 商品説明にとどまらず、業界課題や思想を語る記事が企業のイメージを形づくる
👉 これは直接的なリード数に現れなくても、中長期的に競合との差別化に効いてきます。
2. 採用
- 「どんな知識を持った人が働いているのか」がコンテンツから伝わる
- 技術ブログや事例記事は、求職者にとって魅力的な情報源
- 「この会社で働いたら成長できそう」と思わせる
👉 コンテンツは、求人広告よりも自然な形で「働く場の魅力」を伝えられる。
3. 営業支援
- 営業担当が顧客に送る資料として使える
- 製品説明に加え、業界課題を整理した記事は「導入前の教育素材」として活用できる
- 説明の属人性を減らし、営業効率を高める
👉 この視点では、コンテンツは単なる集客資産ではなく「営業活動の武器」になる。
KPIに取り入れるべきか否か
ここで本題です。
これらの「副次的な効果」を、コンテンツチームのKPIに組み込むべきなのでしょうか?
選択肢1:マーケティングKPIに限定する
- メリット
- 測定がシンプル(PV、CV数、リード数など)
- 集客効果に集中できる
- デメリット
- ブランディングや採用効果が無視され、評価されにくい
- 長期的に価値を発揮していても「数字に出ない」ことで予算が削られる可能性
選択肢2:ブランディング・採用も含める
- メリット
- コンテンツが持つ多面的な価値を正しく評価できる
- 組織内で「コンテンツ=マーケだけのもの」という認識を超えられる
- デメリット
- 指標化が難しい(ブランド好意度、採用応募数への寄与など)
- 評価が曖昧になり、責任の所在が不明確になる可能性
折衷案:一次KPIと二次KPI
筆者としては、KPIを「一次」と「二次」に分けるアプローチが現実的だと考えます。
- 一次KPI=マーケティングに直結する指標(流入数、CV数、リード獲得数)
- 二次KPI=副次的に貢献する指標(ブランド調査結果、採用応募経路、営業利用率)
この二層構造であれば、経営陣への説明もしやすく、現場もバランスを持って運用できます。
事例:二次的効果を活かした企業
技術ブログで採用を強化したIT企業
あるSaaS企業は、技術ブログをエンジニア採用の主要チャネルにしました。SEO的には競合記事に埋もれていましたが、応募者の多くが「御社の技術ブログを読んで応募しました」と言っていたのです。
👉 集客効果は限定的でも、採用KPIに直接効いた事例。
ホワイトペーパーを営業が活用した製造業
製造業のBtoB企業では、マーケチームが作成した「業界課題の整理資料」を営業がそのまま商談資料に使用。結果としてリード獲得数だけでなく商談成立率の向上につながりました。
実務での運用のポイント
-
目的を明示する
- 記事を作るときに「これはSEO狙い」「これは採用ブランディング狙い」と意図を明確にする
-
評価を分ける
- マーケティングチームのKPIはあくまで集客中心
- ただし、成果報告時に「副次的効果」も併せて提示する
-
組織横断で共有する
- 採用担当や営業担当と連携し、コンテンツの活用方法を共有
- KPIも「共通資産」として扱う
まとめ
- コンテンツマーケティングの主目的は「集客」であり、KPIもそこに置くのが基本
- ただし、現実的にはブランディング・採用・営業支援にも効果が波及する
- KPIを一次(集客中心)と二次(副次効果)に分けるのが現実的な解
結論として、**「集客以外の意義も持たせるべき」**です。
ただし、それをKPIの「一次指標」として扱うのではなく、副次的な成果を正しく可視化する工夫が必要です。
コンテンツは「集客マシーン」であると同時に、企業活動全体を支える「知識資産」でもあります。
その二面性をどう評価するかが、コンテンツチームを持続的に成長させる鍵となるでしょう。





