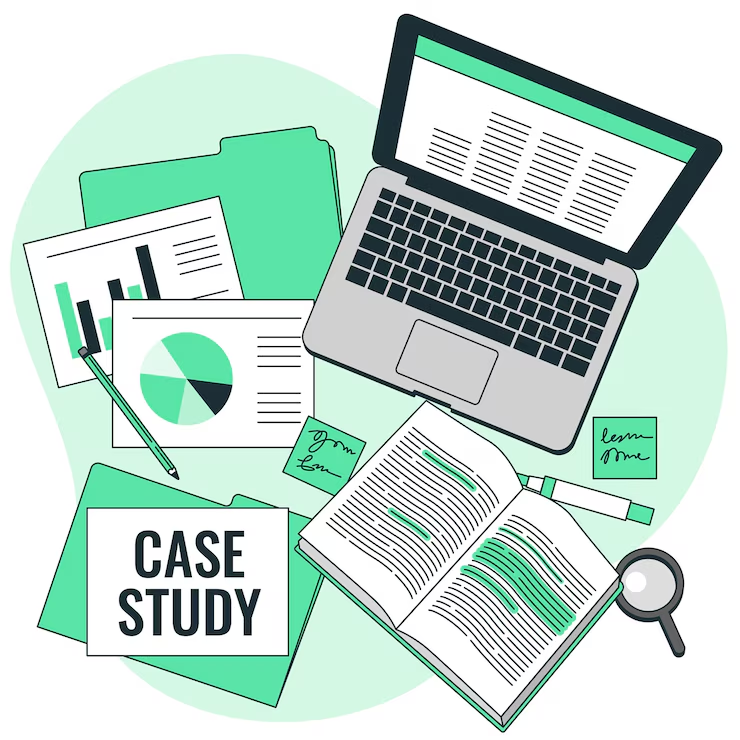
コンテンツが枯れる?──そんなときこそ「事例インタビュー」を仕組み化せよ
コンテンツが枯れる?──そんなときこそ「事例インタビュー」を仕組み化せよ
BtoBマーケティングを続けていると、誰もが一度はぶつかる「ネタ切れ問題」。
特に製造業など、商材のバリエーションが限られる領域では、発信するコンテンツがすぐに尽きてしまうという悩みを多く聞きます。
そんなとき、最も効果的かつ再利用性の高いのが「導入事例インタビュー」です。
とはいえ、
- 「簡単にお客様が話してくれない」
- 「社名は出せない」
- 「そもそも効果が数字で語れない」
など、実際に取り組むと数々のハードルに直面するのもまた事実。
この記事では、事例インタビューを“継続的に回す仕組み”として取り入れる方法を解説します。
なぜ今、事例インタビューなのか?
事例コンテンツは以下の3点で圧倒的に強力です。
✅ 顧客視点で語られる信頼性
実際の利用者の言葉は、自社が発信するよりも数倍の説得力を持ちます。
✅ SEOに強い
「製品名+導入事例」などの検索ニーズに合致し、集客チャネルにもなります。
✅ 営業資料にも活用できる
Webサイトだけでなく、営業時の裏付け資料としても重宝されます。
よくある3つのハードル
-
インタビューOKが出にくい
社内設備に関する話題は公開が難しく、「どこまで話していいかわからない」と断られることも。 -
社名・担当者の公開NG
匿名にすると信頼感が下がり、コンテンツとして使いづらくなってしまいます。 -
効果が定量化できない
「30%効率化」や「年間●時間削減」といった数字が出せないと弱く感じられます。
ハードルを越える6つの工夫
-
匿名でも構成で勝負する
「〇〇業界の生産技術者」などの表現で、役職や課題ストーリーに焦点を当てれば十分訴求力は出せます。 -
動機ベースで語ってもらう
導入後すぐで成果が見えていなくても、「なぜ導入したのか」「当時どんな課題があったか」でコンテンツになります。 -
社内やテストユーザーで“練習”する
関係の近い顧客に「お試しでインタビューさせてください」と依頼すると心理的ハードルが下がります。 -
動画インタビューで負担を軽減
Zoomで収録し、最低限の編集だけで動画化。表情や声の力で信頼感を高めつつ、記事化も省力化できます。 -
顧客のメリットを明示する
「御社の広報にもなります」「公開前に必ずご確認いただけます」と説明すれば、安心して協力してもらえます。 -
公開範囲を段階的に提案
「まずは営業資料向けのPDFだけに使いましょう」→「後日、社名付きでWebにも出せたら嬉しいです」と2段階に分けて提案します。
OKをもらいやすくするコミュニケーション例
- 「御社の取り組みが業界の参考になります。ぜひお話を聞かせてください」
- 「取材協力のお礼として、プロの撮影データも共有させていただきます」
- 「他社事例も多数掲載しており、御社だけが目立つわけではありません」
※ 営業経由ではなく、広報部門や経営層を通じて依頼するほうがスムーズな場合もあります。
継続的に回すための“社内の仕組み化”
事例化は単発で終わらせてはもったいない。以下のように社内の体制を整えましょう。
● 役割を明確に分担する
| 役割 | 担当業務 |
|---|---|
| 営業 | 候補顧客を選定し、協力依頼 |
| マーケ | 台本作成・インタビュー実施・記事編集 |
| 制作 | デザイン・公開・SNS等の展開 |
● 事例候補リストを作る
- 顧客名
- 導入製品
- 公開可否
- 進捗状況
→ スプレッドシートなどで営業と共有
● インタビュー台本をテンプレ化
- 課題
- 選定理由
- 効果
- 感想
このフローに沿った質問集を整備しておくと、誰でも進行しやすくなります。
● ワークフローを標準化する
営業がOK取得
↓
マーケが日程調整&質問送付
↓
インタビュー(Zoom可)
↓
原稿作成・顧客確認
↓
公開・展開
● Notionやスプレッドシートでチェックリスト化すれば、引き継ぎもラクです。
● KPIを設定し、定例化する
「月1件インタビュー公開」などの目標を立てると、継続のペースが守れます。
● 営業連携をインセンティブに変える
事例に協力してくれた顧客には特典を、取材を取ってきた営業には表彰やプレゼントなどを用意すれば、組織全体で動きやすくなります。
まとめ:仕組みで回すから継続できる
導入事例コンテンツは、「質が高いかどうか」ではなく「回せる仕組みがあるかどうか」が成功の分かれ道です。
誰が、どのタイミングで、どの手順で、どこに残すか。
この流れをテンプレート化・習慣化することで、
コンテンツに困らない体制ができあがります。





