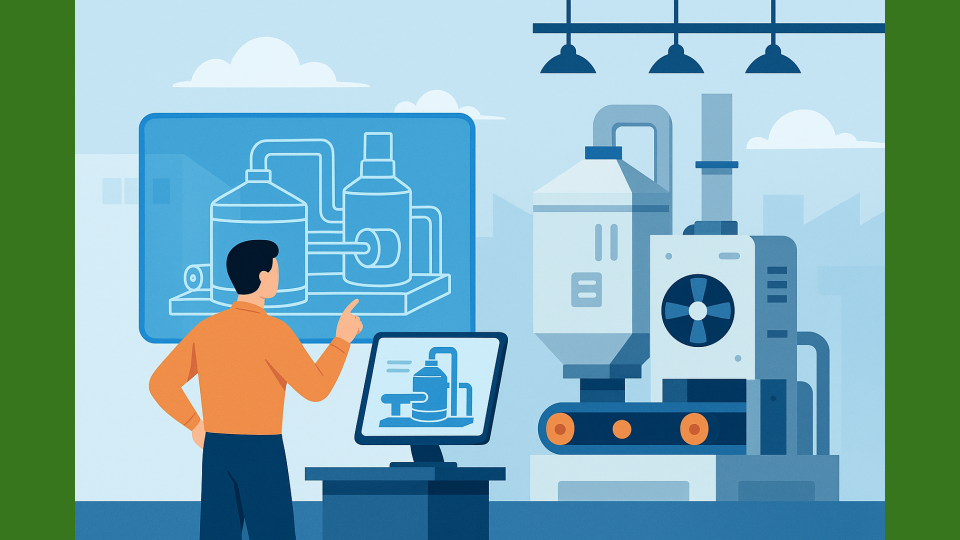
製造業DXを“体験DX”に変える──マーケターが知っておくべきデジタルツインの可能性
近年、製造業の現場では「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が日常的に使われるようになりました。
しかし、実際に進められているDXの多くは、業務効率化や設計プロセスのデジタル化にとどまっています。
もちろん、設計・生産の自動化やペーパーレス化は重要です。
ですが、DXの真の目的は“効率化”ではなく、顧客体験の変革です。
製造業が次に目指すべきは、単なる業務DXではなく、**体験DX(Experience DX)**です。
その中心にあるのが、近年注目を集める「デジタルツイン」という概念です。
デジタルツインとは何か──単なる3Dデータではない
デジタルツインとは、現実世界の製品・設備・環境を、デジタル空間上でリアルタイムに再現する技術です。
もともとはNASAが宇宙船の状態を地上でシミュレーションするために提唱した概念で、製造業においても急速に広まっています。
たとえば以下のような活用があります。
- 設計フェーズ:CADデータをベースに、構造や挙動をデジタル空間で検証
- 生産フェーズ:IoTセンサーと連携し、機械の稼働状況をリアルタイムで可視化
- 運用フェーズ:メンテナンスや異常検知をシミュレーションで予測
ここまで聞くと、「デジタルツイン=設計や製造のための技術」と感じるかもしれません。
しかし本当に価値を発揮するのは、マーケティングや顧客体験の領域です。
製造業DXの盲点:顧客接点が“旧態依然”のまま
設計や生産のDXが進む一方で、顧客接点のデジタル化は遅れています。
営業現場では今なお、展示会や紙カタログ、PDF資料が主な説明手段になっている企業も多いのが現実です。
一方、顧客側の行動は劇的に変化しました。
購買担当者は営業に会う前にWeb上で情報収集を終えており、
「営業に会う頃には7割の意思決定が終わっている」と言われるほどです。
つまり、顧客が“体験する情報”そのものを変えなければ、DXは完結しません。
この「体験のDX」を支える鍵こそが、デジタルツインのマーケティング活用です。
マーケティングにおけるデジタルツインの活用
① 製品の「構造」と「価値」を直感的に伝える
BtoB製品、とくに産業機器や装置などは、複雑で言葉では伝わりにくいものが多いです。
カタログにスペックを並べても、顧客が理解できるとは限りません。
デジタルツインを活用すれば、実機を3D空間で再現し、動作や構造を体験的に理解させることができます。
これは単なるCG動画ではなく、ユーザーが視点を操作し、パーツを選択し、動作を確認できるインタラクティブな体験です。
たとえば、「装置の中でどのようにワークが流れているか」「エア駆動とサーボ駆動の違い」など、
言葉や図面では伝わらない価値を、リアルに“体験”として伝えられます。
② Web展示会・営業資料の「リアル化」
コロナ禍以降、オンライン展示会やウェビナーが一般化しましたが、
「動画を流すだけ」「PDFを置くだけ」のケースも多く、リアル展示会ほどの訴求力が得られないという課題がありました。
デジタルツインを使えば、3D空間上に製品展示ブースを再現し、来場者が自由に体験できる
“バーチャル展示会”を実現できます。
実際、Vizlaboのようなサービスでは、動画と3Dモデルを組み合わせた「インタラクティブな展示空間」を提供し、
顧客が自ら操作しながら製品理解を深める仕組みを構築しています。
このような体験型コンテンツは、MA(マーケティングオートメーション)やCRMと連携させることで、
「誰が・どの製品に・どれだけ興味を持ったか」という行動データを取得でき、営業活動の精度向上にもつながります。
③ 営業活動を“体験ベース”に再設計する
営業資料や提案書の中心がPowerPointから3D体験に変わると、
商談そのものの構造も変わります。
営業が一方的に説明するのではなく、
**顧客と一緒に製品を動かしながら課題を発見する「共同探索型の営業」**が可能になります。
この変化は、営業スキルよりも**体験設計(UX Design)**の発想に近いです。
つまり、製造業のマーケターは、これから「体験を設計する人材」になる必要があります。
経営視点で見たデジタルツインの価値
① 資産としてのデータ活用
設計部門で作られたCADや3Dデータは、従来は製造のためだけに使われてきました。
しかし、デジタルツインの導入によって、それらのデータが営業・マーケティング・教育など、
複数部門で再利用できる“企業資産”へと昇華します。
設計資産を活用してコンテンツを制作すれば、
新規撮影やCG外注に比べてコストを大幅に削減できます。
さらに、一度構築したデジタルツインは、将来的に製品保守・リモートサポート・教育訓練にも転用可能です。
② サービス化(XaaS)への布石
製造業では近年、「モノ売りからコト売りへ」という言葉がよく聞かれます。
製品単体の販売ではなく、利用価値をサービスとして提供する方向です。
デジタルツインは、この転換を支える重要な基盤になります。
製品の稼働データや利用状況をデジタル上で把握することで、
サブスクリプションやリモートメンテナンスといったサービスモデルが現実的になります。
つまり、デジタルツインは“営業の武器”であると同時に、
“新たなビジネスモデルを生み出す装置”でもあるのです。
導入の壁と、突破のヒント
とはいえ、デジタルツインを導入するにはいくつかのハードルがあります。
① 部門間の分断
設計データをマーケティングで活用しようとしても、
「権限」「フォーマット」「目的」が異なるため、連携が進まないケースが多いです。
この壁を超えるには、“データ共有”ではなく“価値共有”の視点が欠かせません。
マーケターが「設計資産をどう見せれば顧客に響くか」を提案し、
設計側と共同で“見せ方”を設計する文化をつくることが第一歩です。
② ROI(投資対効果)の説明不足
「デジタルツイン=高コスト」と思われがちですが、
マーケティング活用のROIは意外と明確に算出できます。
- 展示会出展コスト(数百万円)をオンライン展示に一度置き換えるだけで、長期利用可能
- 営業資料を3D化すれば、1商談あたりの理解時間・提案精度が改善
- 可視化データをMAと連携することで、商談化率の向上が期待できる
このように、一度の制作が複数フェーズで回収される構造を描けるかどうかが成功の鍵です。
③ スモールスタートが可能な時代
かつては高価なソフトウェアや専門人材が必要だったデジタルツインも、
今ではWebGLやクラウドの普及により、ブラウザ上で軽快に動作する環境が整っています。
さらに、Vizlaboのような「3DCG+インタラクティブ体験」をSaaSとして提供するサービスを活用すれば、
自社で専門知識がなくてもスモールスタートが可能です。
これからのマーケターに求められる視点
① 「情報」ではなく「体験」を設計する
マーケターの仕事は、もはや“情報を発信する”だけではありません。
ユーザーが“どう感じ、どう行動するか”という体験設計が求められています。
製造業DXの次のフェーズは、体験DXです。
営業・展示・教育・サポートなど、顧客が触れるすべての接点を“体験”として再設計する。
それを支える技術が、まさにデジタルツインです。
② デジタルツインは「マーケティングDXのハブ」
デジタルツインは、単独の技術ではなく、
MA・CRM・コンテンツ管理・3D可視化といった複数領域を結ぶ“ハブ”です。
その中心に立つのが、マーケターです。
デジタルツインを軸に「顧客体験の見える化」「データ連携」「行動解析」を設計できる人材こそ、
これからの製造業DXをリードしていく存在になるでしょう。
おわりに:体験から始まるDX
DXという言葉はしばしば“システム導入”と混同されますが、
本質は顧客と企業の関係を変えることにあります。
そのための第一歩は、顧客が体験する“製品との出会い方”を変えることです。
デジタルツインは、製造業の価値伝達を“説明”から“体験”へ変える力を持っています。
設計の延長線ではなく、経営・マーケティング戦略の中核技術として位置づけること。
それこそが、真の意味での製造業DX=体験DXへの第一歩です。





